o

4合目くらいまで雪は少ない。トレースはばっちり。踏み固められてほとんど沈まない。トレースは赤テープを素直にたどっていた。
誰もいない山頂は50cmくらいの積雪だった。雪山はやはりいい。
今年もどんどん登るぞ。
途中の松の名前は?。
9:42登山開始、10:10夏焼(なつやけ)峠、10:20,テン場1138ピーク,5テンのテント設営、重たい物をデポし11:10発、12:04/10
恐羅漢山,スキーの板が3組あり、12:37/52台所原作業林道を歩く、13:26先週薮から林道に出た地点、13:34林道終点,谷に赤テープあるも登山路は不明、わかんの跡を辿り尾根を上がる、
13:52朝歩いた登山路に出会い周回完了、14:05テン場到着、
イグルー作成14:15から16:30まで、17:40中村氏テン場到着、
夕食と歓談、21:10就寝
1月12日(月)6:30起床、テント置いたまま8:10出発、8:15夏焼峠、8:
33/37,1166展望ピーク、魔の池、8:52/9:15砥石郷山 9:28,1166ピーク、9:48/10:00テン場、
10:35/45休憩、10:58/11:06,恐羅漢山,11:28旧羅漢,昼食ラーメン,12:10発、12:35/38恐羅漢山、13:15テン場に戻りテント撤収、13:42下山開始、13:47夏焼峠、14:12駐車場、14:23帰路、14:45/15:20いこいの村広島のセラミック温泉¥500 記録 松尾清
イグルーでの宴会は滴と寒さで途中でテントへ。テントのありがたさが身にしみて分かった。
砥石郷山、旧羅漢山は初めて行った。恐羅漢や旧羅漢からは展望が最高。12日は空気の透明度も良く、大山、おそらく四国の山(石鎚?)も見えた。
スキー場が雪不足でスピーカーの音もなくいい雰囲気だった。駐車場からもテン場が近く雪山体験にはお勧めだ。

弟見山

福永
26日
07:00発=13:40弥山山頂14:00=15:003合目テント泊
ルートは積雪の多さから西面の無名沢とボタン沢の間を直登するというもの。夏山登山道の2.1kmに対し1.3kmの距離で頂上台地である。標高差はおなじだから傾斜は急である。
出だしから20~30°のらセル。積雪は膝上から腰近くまである。新雪で安定せず難儀する。樹林帯を交代でラッセル。休憩をはさみながら3時間くらいまではなんとか3:2くらいの回数で分担する。1時間あたり130m程度しか登れない。10時を過ぎたあたりから着いていくので精一杯となる。まだ樹林帯は抜けていない。いったいいつまで続くのか。樹林帯を抜ければ雪は少なくなり少しは楽になるはず。樹林帯を抜けたが、まだ雪はあり苦しい。ついに着いていくことも出来なくなり休憩をお願いする。また登り始める。良く見ると45度もあろうかという雪壁を登っている。アイゼンをつけて慎重に登る。フラットだと足首がやっとの角度。ピッケルとアイゼンを慎重に確実に突きながら登る。
やっと、台地に到着。あと少しだ。だが、ここからも思いのほかあった。三浦氏が縦走路?と自分を見る。旗はあるし台地だとは思うが確信はもてない。旗を良く見ると大山遭難対策協とあり間違いはないようだ。折からのホワイトアウト気味の視界により、避難小屋は10m程度手前でやっと視認できた。だれもいないし、小屋も簡単には入れない。早々に下山を開始する。時間切れにより縦走は中止した。もっとも三浦氏も今日の積雪だと山頂までで精一杯だと思っていたとの事だった。
夏山登山道の下りも視界が悪く旗だより。それでも分かりにくいところがあり、三浦氏が先行し確認することもあった。せっかくのテント泊準備であるので3合目付近で雪中泊とする。三浦氏のフライパン料理を堪能した。
技術、体力、人格どれをとっても超一流の人であった。こんな人と知り合えたのは一生の宝だ。体力的にはハードでバテバテの山行だったが、収穫も多いもので大満足だった。


三浦氏はそれを承知でバリエーションの開拓を行う模様。
そういば大山の時に冬に沢からつめる構想を述べていた。
林道を少し行き、ついに沢ルートに入る。徒渉やトラバースが頻繁にある。たしかに尾根沿いのルートよりかなり難易度は高い。雪もザラメ状でズボズボ状態。しょっちゅう踏み抜く。アイゼン、ダブルアックスで進み。デブリがそこここにある。F5前から危険と判断し、右岸に高巻く。そのまま尾根に登り三ツ倉に登る。脆弱な雪の為這い這い状態だった。山頂では吹雪模様でコンパスでルートを見つけ13:00山頂到着。食事か?と思ったが、まだ安全ではないとの判断で下山を急ぐ。そのときは?と思ったが、山頂部は広くホワイトアウト状態になると危険であるとの判断だったのだろうと推察された。尾根に上がる判断といい、よい経験になった。

9:15出発、9:21藤本新道登山口、わかん装着、10:25/30休み、10:40稜線に出る、
11:10/12:00丸子の頭で昼食、中村氏が追いつく、ここまでは順調、以後樹林など
でルートファインディングに苦労する、13:28/32奥三倉、14:12,1328ピーク、14:
27/42十方山、15:48十方山林道の水越峠の西に下り立つ、16:28水越峠?6:45十
方山登山口、17:50二軒小屋着
下山は予定のルートを左(西)にはずし1時間のアルバイトとなった。
雪山のルートは危険箇所がなければコンパスを優先したほうが良いと感じ、よい勉強になった。
東登山口付近でテント泊。
朝、6時出発。
行き先は、由布岳北側の大崩(大崩落しているとこと)。
作業道を歩き、堰堤を越えて、目の前には大きな岩の壁。
三浦氏が登攀を試みる。
自分がロープで確保する。といっても、支点無し、セルフも取れない。場所は急な斜面の途中。三浦氏が落ちれば2人とも滑落、大怪我は間違いなし。三浦氏は「落ちたらロープは流してくれ。でないと2人とも落ちるので」。
自分は「というわけには....」。...恐怖。
近くで岩がバラバラと落ちている。岩は泥の間に埋まっているものも多く、いつ落するやら。頭の上部にもそんな石がたくさん見える。
当然、登ろうとして持とうとする岩も剥がれ落ちないとは限らない。三浦氏はピッケルで岩をたたき、確認する。
クライミングシューズだとそれほど難しくないと思うが、足にアイゼン手にはピッケルでは三浦氏といえども簡単ではない。結局、空荷でショルダーで登った。
上の岩にロープを結び、ザックを引き上げ、その後自分が登る。もちろん今度は三浦氏が上で自分を確保。
さらに上に行くには同じことの繰り返しだが、初めての場所で、上の状態がわからず、ロープを岩に確保する支点を作るハーケン類も持ってこなかったので、無理して行ってもし登れない壁があり、引き返そうとしたとき、支点がないと懸垂下降できない可能性があり、ここで、撤退。
一旦最終堰堤まで戻り、すぐ左の尾根を登る。もちろん登山道なんてなく、積雪したヤブの急坂(40度くらい)を登る。標高差で100mくらい登ると岩で行き止まり。仕方なくまた引き返し、さらに左の尾根から登る。ここも積雪したヤブの急坂。登るにつれ積雪
量が増しラッセルとヤブこぎでどんどん体力を消耗する。
2.5時間ほどの苦闘の末、大崩のの最上部あたりに出る。良く見るとトレースが見える。誰か日曜日あたりに登ったようだ。
こんなことをやる人が他にいるのか!と感心する。
大崩はほとんどが垂直の壁になっているが、このあたりだけなだらか(30度程度)となっていて、大崩の中に下りる。
大崩の中を少し登る。西峰と東峰のお鉢巡りの中間部あたりはもうすぐ。あとは下りがほとんど。出発から既に5時間以上ほとんど登りばかり、それも普通のところじゃないので相当ばてている。でも、登りはあとちょっと。ホッとする。
「福永さん、悪いけど、この中を下りてみたいんですが」。
「エッ、もし途中で降りられなくなったら?」。
「登り返す」。
「...嘘じゃろー....」....「いいですよ、..まいったなー」。
バテバテの自分に対し三浦氏はいたって元気。体力、気力ともたっぷりの雰囲気。スーパーの人ならどおってことはないが、スーパーマンと2人の山登りは本当に大変。得ることも疲労感も半端じゃない。
結局、40度くらいの雪壁を標高差で150m~200m近く下り、やはり予想通り下りられず上り返し。その時の自分の落胆ぶりは想像出来るだろう。
やっとの思いで登り、食事を含めて20分ほど休憩。少し体力が回復し、お鉢巡りをして東登山口へ降りました。
下山は15時30分。
6時出発だから9時間30分。バテバテの一日だった。
出発は9時ちょっと前。下山は13時だった。
最近8時間位は普通だし、単独故自分のペースで登れ楽な登山だった。
雪も大してなく稜線上に締まった雪が有る程度。無雪期と大してかわらないスピードで歩けた。途中の道標から南へ尾根があり地形図で見ると寂地峡から直接登れそうに思えた。ただし冬だけ可能なのかもしれない。来年は考えてみるのも悪くない。途中、長野からの登山者に出会い、「裏山の6月程度だから、長靴で十分」とスパイク付長靴を見せてくれた。右谷へ登り下りるところだった。GPSの軌跡は地形図とほど一致しているが、寂地山直下から林道へ下りる最初の部分が地形図と反対に、尾根を横切り東側の緩やかな谷を下降していた。
いよいよ、雪山も終わりの気配。もう一度積雪を待望する。
前夜21:00家を出発し、22:30頃願成就温泉にて落ち合う。鹿野の峠で-8°であり大山は相当の寒さが予想される。
出発から6時間で3:00過ぎに駐車場着。-10°である。1時間車で仮眠。5時過ぎに登山開始。堅雪の上に30cmの新雪が乗っている。雪質はパウダーなので軽いが、案外きつい。いつもどおり三浦氏は快調に登っていく。セカンドにも関わらず着いていけず遅れ気味となる。県民の森付近で1本。鳥越峠に行かずキリン峠直登を行く。途中にはブナ林はあるが、なぜかあまり大木はない。
尾根の西斜面をトラバース気味に進み、7:30キリン峠着。出発から2時間半を要した。8合目くらいから上は既に雲がかかり、時折吹雪き模様の雪が顔に当たり痛い。
2月のリベンジである。三浦氏の勤務の都合で、0:00頃の空港出発となった。3時頃東登山口近くの前回と同じ場所に駐車。2時間の車中仮眠を取る。
前回と同様最初の難関をショルダーで越える。CLはロープを着けているが確保点がないのでフリーと同じ状態。落ちれば怪我は免れない。20mで唯一古くて伸びて楕円になったリングボルトがある岩がありそこで1P目。続いて自分が登るが、前回より難しい。かなり怖く感じられ、今更ながらCLの力量を感じる。しかし、CLもやはり「怖かった」と言っていたのでかなりの場所のようだ。2P目はこのリングボルトでトップを初めて確保出来るので多少安心だが、最初の乗越しが難しく、CLはハーケン、杭を打つ。終了点には雪に埋もれた木の枝が露出しており、確保点となる。しかし、雪が深いとこれはない。その場合はもう少し上まで行き、探すしかないのだろう。このPはかなり危ない所もあり、確保なしでは不安だし危険と思う。次のPは岩にシュリンゲをかけ確保点。その次はハーケンで確保点。その次は岩にシュリンゲをかけ確保点。次は割合簡単な所で、ロープなしでも行けそう初めてつるべで自分がリードし岩にシュリンゲをかけて確保点。左下にルンゼがあり、星と焚火のパーティーはそちらを行ったものと思われる。登り始めの最初からルートが違ったようだ。
前回ほどの疲労感はなく、しかもやり遂げた充実感は一杯だった。
CLが23時までの勤務の為、熊毛インターで01時20分に落ち合う。
鳥越峠に向かう途中から予想に反し天候回復。正面に烏ヶ山が見える。CLがしばらく見ている。「せっかくだから烏に行って南峰から尾根をつたい帰ろう」。
ところで同行の岡部くんによると、大学山岳部は絶滅寸前状態。そんな中、彼は募集もしていなかった山大山岳部に自ら入部希望し「ほんとに?」と驚かれたとか。今年の冬合宿も厳冬の槍ヶ岳に2人で登ったそうで、やる気満々でまだ20歳過ぎの彼の前途は無限大だ。歳の事をいっても仕方はないが、正直うらやましかった。
21:晴れ
3.21.(日)5:10起床、6:50出発、7:05鞍部標識から勝間ケルン下方をトラバース、7:20上宝珠越し、少し剣谷を下降、8:15/25中宝珠越しで休憩、8:50上宝珠越し、9:05林道横断、9:15/25アイゼン外す、9:40大山寺、10時00分駐車場着(松尾清氏の記録)
19日20:00松尾宅を出発、二台に分乗し下山キャンプ場駐車場へ。
下り18分。
黒岩山は周東町のパストラルホールもあるスポーツセンターの野球場に車を置ける。
ここまで来るとちょっと黒岩山までと強引に出発。不満そうな妻を尻目にどんどん進む。特徴的な岩があったり割合良いコース。妻は途中でギブアップ。自分だけ山頂まで。山頂には大きい岩が鎮座していた。竜ヶ岳もすぐ近くに見える。次回は是非縦走をしよう。
是非知りたかった技術だったので前もって午後から半休をとっていた。
莇ヶ岳まで車で1時間10分
下りは刈り払われたそれらしき道を下るとすぐ岩が現れた。細い鎖とロープ2本が松ノ木に繋いである。鎖は最初になくなった。さらにロープの1本も。最後には細いロープ1本。それも少し届かないが、なんとか下りた。上を見ると登るのは大して難しくはなさそうだった。
2段の鎖の下の方の途中に出た。なかなか面白い岩場だとおもった。
7人パーティーは1時間、自分は38分で登った。一般人の中に入れば結構速いようだ。
帰ると松井のメッツデビューのTV中継をやっていた。

福岡組は鎖場を通り9:55山頂に着いた。鎖場でもたついている一人を置いてさっさと弟見へのピストンへ出発して行った。遅れている太った一人の女性は大丈夫なのだろうかと気になり、そのことを伝えようと赤鬼の岩を下り鎖場に引き返したが既に下の段は終え、最後の鎖のようだった。仕方なく下山した。それにしても冷たいパーティーだ。

今年は萩の末松さんが転落死という非業の死を遂げ、会としても基礎技術は確実に習得する必要がある。8字むすびからはじまり、インクノット、ハーフノット、プルージック、バッチマン、タイロック、懸垂の仕方、支点のつくり方、シュリンゲの収納方、ビレーの方法などを行った。福江氏によると流動分散は最近はしない!との説明は調べてみる必要はありそうだ。
今年初めて(アイゼン岩トレを三浦氏と行ったが)の岩で、国体、米粒、観音を登った。久しぶりなので心配したが、ほとんど問題なかった。
朝の集合時間の陶の駐車場はいつになくたくさんの登山者が集まってきた。
山口山岳会で末松さんの追悼登山とのことだった。
墜落場所には花が手向けてあって、自分も手を合わせ冥福を祈った。
岩をやる以上は死のリスクは隣り合わせで、安全には十分気を配る必要がある。
今回の岩トレは登るだけでなく、基本習得に有意義であった。岩トレシーズンの最初には毎年でもやる必要があるだろう。
快調にすすみ短い急登を登るとあっと言う間に竜ヶ岳。1時間ちょっとだから、おそらくコースタイムの半分。2年前は休憩を含んでとはいえ、竜ヶ岳からの下りで2時間かかったことを考えると、やはり体力は付いている。努力すれば成果は現れるものた。これからのトレーニングに張りが出る。
下りでは途中から坊ヶ原に降り周回の予定だったが、道がはっきりせず、結局ピストンになった。帰りは迷った7分を差し引くと52分というハイペースだった。
迷った場所は帰ってGPSの軌跡とインターネットの情報でみると間違ってはいなかったようだ。もう少し行けばよかったのだが、何のテープも案内もないので引き返したのだった。
竜ヶ岳からは大黒山が近くに見えた。おそらく竜ヶ岳から1時間はかからないだろう。スポーツ公園まで1.5時間。さらに車道を歩き車回送まで2時間とすると大周回ルートで4.5+休憩1時間として5.5時間くらいか?。
近いうちにやってみたい。
時間がないので、車で登れる所まで行く。そこからは標高差はわずか200m、あっと言う間でわずか20分程で山頂へ。山頂には夫婦と4人の女性の2パーティー。笹の斜面がきれいだった。400円の願成就温泉で汗を流し、さらに津和野の道の駅でアップルパイを買い、莇ヶ岳右ヶ谷キャンプ場そばを通り帰宅した。物足りない山登りだったが、妻の希望との折中案としてはまずまずのプランだったかもしれない。
ノーマル直上(5.4)、ノーマル2ピッチ(5・4)、ノーマル3ピッチ(5.3)
もう一度降り、今度はノーマル直上ルートを登る。2ピッチ目が難しいが、今回は割合上手く登れた。クラックの中に入り過ぎないことがコツのようだ。山頂まで登り三浦氏は2勤だそうで、今日はこれで終わり。佐伯さんは宇部山岳会年金組みだそうで、30年ぶりの岩登りとか。昨年錦鶏の滝を一緒に遡行した白髭の方だった。奥さんも含めなかなか上手い。特に奥さんは軽量もあり軽やか。すぐ追い抜かれそうだ。
ライオンの顔(5.4)、ノーマル(5.0)、ノーマル2ピッチ(5.4)、スカイライン(5.7)
2回目は、ライオンの顔を登り濡れているためノーマルルートを経由、ノーマル2ピッチ目を登り、最後はスカイラインだ。以前挑戦し、取り付きでギブアップだったルートで不安。
奥さんは前回自分が出来なかった場所を難なくクリアー。ガバを持つところで結局次が持てずギブアップ。次は自分の番。前回できなかった場所は難しくはなかった。ガバの場所が核心のようだが、午前中のテーブル直上の方が難しいと感じた。最後はノーマルのチョックストーンの場所となり終了。満足度が大きい岩登りだった。岩は面白い。今日はつくづく感じた。
歩行距離24km、標高差±764m
目指すはコバルトライン。2時間ちょっとで188号線へ。そこから昼食は豆吉とし、田布施方面へ少し歩く。豆吉定食は1300円にしてはちょっと量がすくない印象。
五軒屋、伊保木を過ぎ周回。休憩を除き4時間20分程度歩いた。
久しぶりの長距離で左の腰の横が痛い。
よく考えてみると、親父のゆかりの場所。今度は遺影をザックに入れて歩いてみよう。

26日:07:00登攀開始=10:50登攀終了(7ピッチ)=12:30下山
1~3A1
4~7フリー
三浦氏は意に介する様子もなく、準備をする。取り付きは道からすぐ。最初は早速アブミ。三浦氏のようにはいかずまごつく。1ピッチを終了し、三浦氏から膝や足での隙間の作りかた、左右のアブミを交差させないようにとアドバイスをもらう。2、3ピッチも人工だったが、アドバイスのおかげでかなりスムーズになる。
あとはフリー。Ⅳ級程度ということで大したことはない...と思ったのが大間違い。核心部で2箇所大汗をかく。ヌンチャクを持ち、チョンボ棒も使いなんとか登った。
あとでルート図を見ると部分的に人工が混じっていた。その部分で難儀したのだった。
初めての本格的なマルチピッチは人生でもっとも怖く、しかし充実感も一杯の一日となった。
三浦氏に感謝。

搬出システム1/5、チロリアンブリッジ
ちょうど、電柱の根っこで身長ほどのものがあり、対象としては十分だ。おそらく100kg近い重量だろうと思われる。
1/5システムで吊り上げる。裏の7m程の崖で試した。ビナ2枚でガルダーヒッチはすぐれものだった。手を離しても確実に止まる。滑車代わりに2枚のビナ(1枚はヌンチャクの片方)とマッシャーオートロックのヌンチャクの片方、さらに支点用のテープ4枚、マッシャー用のシュウリンゲ1本。ロープは10.21本、補助ロープ1本であり特殊なものは何もない。
思ったより順調に吊り上げ成功。途中根っこに引っかかったりしたがそれでも2時間であった。さらに、チロリアンブリッジにも挑戦。ロープを張るのに1/3を使う。だが、谷が浅すぎて地面を滑るような感じになってしまった。
最後は半マストで2mの土手をおろし搬出終了。
思いの外上手くでき満足であった。

登山口に予定の10:00着。すでに収集を始めている。8名が今小野経由との指示で車を回送する。登山口近くにトタンや農機具の投棄があり写真を撮る。
登山道にはあまりゴミはない。蒸し暑いせいか大して標高差もないと思われるがかなり汗をかく。山頂では恒例の天ぷら。一人一品だったが多すぎてあまった。ゴミの収集は可燃物 12、5Kg 缶、ガラス類 17、55Kgとまずまずの成果だった。
セミナーパークの斜面を使い1/5システムを実践。さらにチロリアンブリッジのやり方の練習も。宇部山岳会の講習会ではその成果が発揮されるだろう。
茶臼山:下松バイパス=36m茶臼山=25m下松バイパス

所要時間 6h30m
下部壁6ピッチ(ルート図では5ピッチ)。上部壁4ピッチ。
5ピッチは隣の壁に斜めに橋のごとく手を突くところから始まる。6ピッチは最初のピンが遠い。リーダーはちょんぼ棒を使用。左の小さなクラックを利用するといいようだが、難しい(A1、11a)。ハングした天井の下を左に抜け登ると天狗の踊り場となる。ここで下部壁終了。
上部壁の取り付きに10分のアプローチであるが、すでに水分不足としゃりバテ&体力不足でバテバテ。途中には5m程の垂直の壁の結びで手がかりを付けたロープでのアプザイレンがある。
上部壁の最初の7ピッチ目は木に支点を取り始まる。薄い草付きや濡れた壁は滑りそうで気持ちが悪い(5.7)。次は木の根っこがあるチムニーを登る。折れそうな根っこを掴んで登った。不安な根っこだがこれがなかったらかなり難しそうだ(10c)。9ピッチ目は最初左へどんどんトラバースすると楽である。その後はスラブで快調に登る(Ⅲ級)。やっと最終ピッチである。ルンゼ状をどんどん進む。ロープが間断なく延びていくので簡単そうだ。バテバテの自分としてはうれしい。と、突然止まる。支点作りかとしばらく待つと「ボルトを抜いてある」と戻ってきた。違うルートを探している。スラブ状を左にトラバースするルートを取った。自分は三浦氏とすこし違うルートに挑戦しレイバックで直上しようとするが行きづまり、足が滑りテンションがかかる。結局指1本が少し入る程度の手がかりと足のフリクションでトラバース。CLと同じルートとなった。最後は足幅のバンドを5m右にトラバースすると最終支点。そこからは見慣れた山頂の岩を歩き終了。疲れ果てたが最高の登山だった。テントで浴びるほどビールを飲んだ事は言うまでもない。


入渓 8:10=9:30林道=10:30入渓地
小瀬川の道の駅を過ぎすこり北上し堰堤が見える場所から200m地点に左から流れ込む赤い沢がアカナメラ谷である。ほとんど滑の沢で大きな滝はない。F1,F2も斜滝でお助け紐もいらない。滑は上流までのびこの沢と特徴とか。上部の小連滝の景色がなかなかよかったが、カメラに納めるのは忘れた。
沢入門編という感じで、アドベンチャーな趣はない。三倉の疲れを取るにはちょうど良かったもしれない。
12時には家に帰り、三浦氏と食事をし別れた。こんばんは夜勤とかであいかわらず驚愕の体力である。

取り付きまでが結構疲れる。大汗をかく。
5ピッチやったが、結局核心部はクリアーできず。
自分の実力はセカンドで5.8程度。
まだまだ超初心者だ。
ハイステップ系と指力のいるものが苦手だ。

車で入渓場所まで移動。
遡行図

遡行図
1153ピークからは尾根、沢、藪ヶ峠へのルートが分かれる。沢沿いを進む。ふみ後はなく、最初は軽い笹薮。しかし水音がするあたりから厳しくなり、沢を下るのは危険なため、トラバース気味に下る。かなりな藪漕ぎ。高度計で藪ヶ峠からのルートと重なるあたりで沢へ下降すると、踏み後があった。昨年、沢から這い上がった場所のすこし手前くらいだろう。それからは高速道路で下山した。
ゆららの湯(450円)入浴後帰宅した。

登山口には看板がある。それより少し前に丸太橋から踏み後があり、おそらくヤブ漕ぎルートだろう。
看板の登山口からすぐに沢を徒渉し、人工林をすこし登ると、幼木植林のつづら折れになる。さらに登ると自然林となり、いい感じになる。
縦走路に出るときれいに刈られている。雀谷山は右へ行く。少し急な坂をアップダウンし10分で山頂の三角点である。視界は全くない。
飯ヶ岳の縦走路を行くと、程なく名物?の「蛇落としの坂」につく。
確かに何の知識もなくこれが現れるとびっくりするだろうが、覚悟して臨めばそれほどでもない。下りはじめから3分くらいカニ歩きで下りるが、それ以後は前を向いて気を付ければ普通に下りれる。最大斜度は40度ほどだろう。
中間部からは傾斜は緩くなる。
鞍部から自然林の雰囲気がよくなるが、登り返しがしんどい。
30度を超える暑さに、水の消費が多い。1.5Lのペットボトルがすでに残り500mL。
地形図で気になっていた国道に下りる尾根にはルートがやはりあった。おそらく飯ヶ岳には最短距離だろう。
飯ヶ岳からは滑ルートを取り、登山口で沢の水を補給。
そこから林道歩きが長い。
せっかくの縦走、周回ルートだが、雀谷山に魅力が乏しいことと、長い林道歩きがいまいちだった。

8:38入渓=9:28休憩9:40=10:50F8(ロープを出す)=11:50F10手前で昼食12:40=14:20登山道(標高1000m)14:30=15:15寂地山頂15:28=16:00ミノコシ峠=17:05駐車場
さらに犬戻の滝の大迫力。ロープを使ったⅢ級登攀のF8(鳥越の滝)とバラエティー一杯。
久々に楽しい沢登りを満喫できた。
昼食は正田氏のうどん。周りにレジャー客が涼を求めて2グループいた。
そま道の20名近いグループとも出会った。
それにしても、よく集まったものだ。ひょとすると結構まとまりの良い会なのかもしれない。
中重氏と林涼子さんに出会った。
沢は犬戻の滝を過ぎてもそこそこ面白い。下りは、林道歩きは退屈なので出来れば山頂を踏むとよい。が、ミノコシ峠周りはかなりハードではある。。今回は時間の関係から、1000m付近で登山道に上がり(すぐ寂地山頂1.5kmの看板のある地点)山頂を踏み、ミノコシ峠から降りた。
沢登、山歩きとたっぷりの一日だった。
大満足であった。
帰って参議院選挙選挙速報もあり、さらにたっぷりの充実した日となった。

入渓地点245m、出たところ500m地点(603と644を結んだあたりです)。
タイム:Pから入渓地点間(14分)
入渓地点08:21=車巻の滝上部9:08=終了点10:05=入渓地点10:36。
狗啼沢かと思ったが、岩倉沢左俣だった。
どちらも中級で、時間は岩倉沢の方がながいので、自分としてはラッキーだ。
F3は2段の滝をロープを出す。段毎に切り、2ピッチとする。
F4は車巻の滝と命名してあるように8mの滝で、立派な釜も持っている。
リードは逆層とコケで滑るため無理で右岸を巻き上からロープを垂らす。
ロープ確保で登り途中からロープでテンションをかけて左岸に位置を変える。
落ちても釜があるので割合プレッシャーは少ないがやはり8mあるので慎重にいかないといけない。
F6は右足が開いて上がればステップがあり難しくはないのだが、自分は案の定足が開かず届かない。結局右岸を巻いた。
F8は念のためロープを出す。出さなくても十分安全だと思ったのだが。
ロープを出すことは恥ずかしいことではない。危険を察知出来る能力であり、200%の安全確保がなければ、沢や岩は長く続けることはできないのだ。
良い勉強になった。
今年は梅雨明けが入梅が5月、明けが7月11日と例年に比べ早い。
沢をたっぷり楽しめそうだ。

あとは記録なし。
天狗ヶ城=北千里ヶ浜=大曲
体が大きくはない彼女だが、ゆっくりながらも弱音は吐かず着いてくる。
初めてにしては少し長めのルートを完歩した。
星生山の岩場もなんなくこなし、今後に期待大であった。
自分は前夜22:30空港発で、小月~小倉東まで高速、その後は由布岳西側の自衛隊基地そばを通り2:30牧ノ戸着。大曲で車中泊してこの日を迎えた。
3人は牧ノ戸温泉で泊まり、自分は19日の勤務に備え4時間半を眠気に耐えながら空港まで運転。
明日夕方にはついに北岳バットレスに出発となる。

登山口4:50=6:30二股=7:50下部岸壁取付。
8:30登攀開始16:00登攀終了。
16:23=16:45北岳山頂16:50=17:15肩ノ小屋
岩は硬いと書いてあるが、もろく崩壊している場所も多く、ホールド、スタンスは注意する必要がある。このあたりがゲレンデと大きく違うようである。
また、草付きや濡れている所も多い。
5Pは左へ大きくトラバースしハング上で切る。トラバース場所はかなり注意しても落石を引き起こしてします。平日で独占状態ではあったが、他のパーティーがいる場合は取り付きたくない気がする。
6Pは直上クラック15m、7Pクラック、Ⅴ級の核心。中間部がすこしいやらしいが、上部にガバがある。8PはⅣ+だが最初が登れない。ぐらつくハーケンでヌンチャク使用で越えた。9Pは上部が難しく、やはりヌンチャク使用となった。10Pは左上後クラックを直上する。狭いクラックは草が生えており、水も少し出ている。滑りそうで怖い。三浦氏もここは気合いが入ったと言っていたが、結局ロープにつかまり50cm登るとガバがあり越えられた。支点にしたナッツが回収出来ず残置となってしまった。
11Pはピラミッドフェースの頭を右に巻き、四尾根ルートとなる。
四尾根ルートはピラミッドフェースに比べるとずいぶん簡単である。しいて言えばⅤ級のマッチ箱の3mの垂壁が難しいが、右のリッジに回るとⅢ級である。疲れているのでリッジを通った。
マッチ箱からは懸垂で降り、あとは簡単な3ピッチで終了となった。
今回は1ピッチをdガリー大滝に取ってしまい、よく見ると浅い凹角は右にあった。
山頂に達するにはいろんなルートがあるが、アルパインルートが一番困難であるのは間違いはないだろう。それだけに達成感の大きさは他と比較にならない。
途中で大樺沢から登山者が見ていたが、なかなか快感であった。
山頂から肩ノ小屋に向かう途中ブロッケン現象が祝福してくれた。

奈良田12:30 入浴後22:40帰宅。
高速料金 32600円。走行距離1800km。
北岳からは間ノ岳、農鳥岳と稜線がくっきり見える。
三浦夫人は昨日農鳥小屋に1:30着。そしてこの日は4時に出発、奈良田に11時頃には降りたということだった。コースタイムよりおそらくずいぶん速いはずで、健脚ぶりをいかんなく発揮した。
快晴の北岳バットレスを昨日の達成感を思い起こしながら過ぎ、超特急で広河原に到着。
時間解放の11時~12時に間に合いすぐに奈良田に向かって出発した。
この日は甲府で40.4度を記録し、韮崎付近でスーパーに立ち寄った際にその異常な気温を体感した。サウナのように熱を感じる気温だった。


河津より入渓 8:20=10:20 1153ピーク10:30=尾根をヤブこぎの後ノボリヨウ谷から下降=河津11:40
ロープが必要な滝はないが、結構いい感じの滝も多く、自分が記録したもので12個、三浦さんの記録で7個(自分が独立した滝としたところを、小滝連とまとめていたよう)。
白い水しぶきが筋の様にゆるい傾斜ではあるが30mくらい続いているところもありなかなかよい。
三浦さんも、この沢は水量が多いときがちょうど良いようだとの感想だった。
ここは下山がむしろ核心。
1153から尾根沿いに下降したが、途中からはひどいヤブ漕ぎでしかも尾根も分かり難い。
下降の際見たノボリヨウ谷はしょぼい沢だった。

水量はずいぶん多く、しかも水は冷たい。
河原歩きだが水量のせいで結構面白い。
途中で最初狙っていた大町谷の出会いで、平坦だと思っていたのが以外にいい感じだったので急遽変更した。
F13段5mを左から高巻いた。しかし、すぐ地形図どおり平坦となり中津谷へ引き返した。
終了点近くで飛び込み泳いだ。
雷鳴がとどろき始め急いで道路に上がり終了。
小川林道終了点からすこし国道を匹見方向に行った場所の河原にキャンプ場があった。
キャンプには快適な場所のようで、平日にも関わらず数組の人がいた。
kg)
初めて背負子に水タンクを背負い登った。
かなり急登でこたえる。トレーニングにちょうど良いが、車の置き場所が問題だ。
港からだとちょっと長い。今回は二股に置いた。
下りは新ルートを通る。次はこれを登ってみよう。階段が多く面白くなさそうだがトレーニングにはよさそうだ。
ここの山頂は何回登っても最高の景色だ。
肩がらみ懸垂訓練

車道から新登山道を登る。
入り口には愛宕神社登山口の石碑あり。
それにしてもきつい。一昨年の祖母を思い出した。
家に帰り、西穂~奥穂を目指し、肩がらみ懸垂を体験した。
足が摩擦で痛い。空中懸垂も可能だがせいぜい2~3mくらい。
国体ルート1ピッチ目くらいなら大丈夫と感じた。
シュリンゲでハーネスを作り半マストも試した。こちらは十分大丈夫だった。
山頂まで1時間弱をノンストップで登れる。
山頂で、前回会った人にまた会った。
水タンクを二人が触ってその重さにびっくりしていた。
ボッカには手ごろなルートだ。
気力により琴石と使い分ければよさそうだ。
イノシシと思われる土を掘り返した跡がたくさん道沿いにあった。
先週よりは少し楽な感じがした。

入渓8:20=9:40終了点
終了点すぐ下の滝もなかなかきれいであった。
台風の影響が残り、水量は相当多かった。
誰かが写真を撮っていた。
入渓谷10:10=12:15黒ヌタ滝
黒ヌタは左からの方が楽。
真ん中は難しいが、最初の場所で逆手のパーミングがいいようである。
キャンプ場でソーメン。一人2束ちょっとで少なかtった。
午後は錦鶏沢。ここも水量が多く面白い。
水中にガバがあるところではそれをしらないようで、みなショルダーや上からのお助け紐だった。自分はガバを持ち、唯一補助なしで登った。
雌滝はリードは左のルンゼを登ったほうが安全。木で支点を取る。
帰りに見た雄滝はトップロープでも難しそうに見えた。

12日
京都23:00=さわやか信州号=5:25上高地
上高地5:37=6:27明神池6:32=7:10徳沢ロッジ=7:28新村橋=8:04横尾=8:43一ノ俣=9:09槍沢ロッジ9:24=10:08大曲=10:50天狗原分岐11:00=11:45坊主岩小屋12:03=12:25殺生分岐=12:40休憩12:50=13:20槍岳小屋
(休憩58分 歩行6時間45分)
13日
槍岳テン場5:57=6:15大喰岳=6:38中岳=7:20南岳7:35=9:22A沢のコル=10:30北穂岳10:50=12:20涸沢岳12:50=13:00穂高山荘
(休憩時間75分 歩行時間6時間8分)
14日
穂高山荘テン場5:26=6:36涸沢山荘=7:34橋=8:21横尾山荘8:30=9:15徳沢ロッジ9:25=明神池(休憩10分)=10:46河童橋
(休憩28分 歩行時間4時間52分)
12日5:30上高地着
電車のトラブルで12日に上高地着。
5:37バスセンター発。
快晴。サー行くぞ!!。
大曲あたりから傾斜が急になり、高度もどんどん上がりきつくなる。3000mで酸素濃度は0mに比べ7割になるのだから当然かもしれない。
ぜいぜい言いながら1:20槍岳小屋着。
テントを張るがほかにはいない。小屋だと8500円、テントは500円。みんな金持ちだ。
槍は登山道。鎖は要らないしはしごだってなくてもOKかも。山頂は10人ほどのスペース。
13日は大キレット越え。南岳手前で声を掛け奥穂まで行くという中村氏と同パーティーをくむ。
長谷川ピーク、飛騨泣き共に拍子抜け。また鉄板のステップまであるのはちょっとやりすぎ。
北穂の登り。涸沢岳の登りはきつい。
14日は奥穂~西穂の予定だったが、夜半から雨がテントをたたき早々に中止を決断。
5:26穂高山荘発、10:46バスセンターに下山した。
午後からは天気が回復し、パンタグラフ事故が恨めしい。
予備日があれば沈殿も出来たのだが。
全体の印象は、すくなくとも岩を少しでもやっている人なら怖さは微塵も感じないと思う。
実際、槍、大キレット、北穂~涸沢岳とたくさんの鎖、はしごがあったが鎖はほとんど使わず、はしごも使わなかったところもあった。
今回、奥穂~西穂は雨で(岩は濡れるといやなので)中止したが、それほど残念とは思わなかった。
おそらく大キレットより極端に難しくならなければ(そうなると一般ルートにはならない)なんら問題なく通過できると前日の南岳~涸沢岳の通過で確信できたからだ。
山岳会に入る前にアザミヶ岳の鎖場で固まったことを考えると自分が別人のように感じた。
もっとも、今回の鎖場よりアザミの鎖の方が難所かもしれない。
自分の印象では、大キレットより北穂~涸沢岳のルートのほうがよほど危険。
あそこを余裕でこなせれば大キレットなんてなんでもない。おそらく奥~西も大丈夫でしょう
今回の山は自分のレベルを確認する意味もあった。
山岳会の仲間や、エキスパート氏と沢、岩などやっているうちにいつの間にか自分でも驚くほど岩稜にたいしては力がついていることを実感できた。
まったく怖さを感じないのがむしろ怖いとさえ思う程。
長谷川ピークの場所も鎖を持ってトラバースするようになっているが、狭い背中部分を通った。
途中で、バカは止めようと冷静になり本来ルートに戻ったが。
今回の経験ですくなくとも一般ルートならどこでも行かれる事がわかったのが大きな収穫。
北穂に到着したときヘルメット姿の男女が2人。どうやら東尾根のバリエーションルートを登ってきたらしい。
槍ヶ岳の山頂からも、あの有名な北鎌尾根が見えた。
夢は拡がる。
むすび投稿リポート

牛小屋高原下見のあと再び二軒小屋
二軒小屋10:50=11:21登山口取り付き(カーブミラーの所)=11:26倒木=11:29倒木=11:32=11:38=12:07倒木=12:16旧恐羅漢山12:25=(一番左を下る)=12:37大きな倒木=12:48(道間違えで引き返し開始)=13:06旧恐羅漢13:09=(真ん中の道)=13:26恐羅漢13:36=14:07牛小屋高原=(滝見物10分)=14:40二軒小屋
台風18号の影響が気になる。通行止めのため十方山の道を通ったが登山口には「倒木、がけ崩れのため立ち入り禁止」の看板が。
二軒小屋~旧恐羅漢~恐羅漢~牛小屋高原に降りた。夏焼峠は通らなかった。登山道はまったく問題なし。ひょっとすると後日チェーンソー持って..なんて事も考えていたので安心した。倒木も少しはあったが、すべて過去のもので今回の台風とは関係ないようだった。
帰ってやまびこMLにて19日にやまびこ4人が登山道整備をしたと知った。
台風18号の影響で山桃の木が2本倒れていたが思ったほど荒れてはいなかった。
山頂にはいつもの60代と思われる男性が。
確か、3回目だと思うがまだ名前は知らない。
登山道は枝を処理したりだいぶ整備はしたそうである。
しばらく話して下山は一緒に降りた。
下山で歩き慣れているか分かるとものの本に書いてあったが、なかなかしっかりした足取りだった。
次は名前を聞いてみるとしよう。

自宅=恐羅漢2H30M(内黒峠経由)
恐羅漢から台所原に降りていく登山道の両端50cmくらいの笹がきれいに刈り払っってあった。台所原で登山者らしき2人に追いついたので話を聞くと、刈払いの仕事で匹見から来て帰るところとの事。これでバスハイクの登山道整備は完璧だ。
道路情報:
内黒峠経由の公園線は電光掲示では通行不可だったが、まったく問題なく通行できた。一応目安は戸河内側の上り口が通行止めになっていなければ大丈夫と思う。
傘が結構良い。風さえ吹かなければ快適。
切窓西壁

トンネルを越えてアプローチ15分。目の前には垂直の岩壁が。
1PはジェードルでフリーⅣと書いてあるがとんでもない。難しい!。
結局A0となる。特に上部のハング気味の場所はフリーじゃ絶対無理だ。
2Pはルート図ではA1だがフリー又はA0で越える。ジェードルのクラックにハンドジャムでなんとか持ちこたえる。
3PはA2。ハングをアブミで越えるという初めての経験。
レストフィフィが短すぎてうまくかからない。腕力が徐々になくなる。ハングの天井にアブミでだらしなくぶら下がる。足の下には何もない。怖い!!。
結局ギブアップ。懸垂で撤退。
あーー!!、挫折感。
でもめげずに今夜宮崎に岩登りへ行く。懲りないのだ。

7:30 美しいトラバ-ス開始~10:30終了~11;00取り付き~上鹿川11:45~比叡山三峰下水場
12:45 白亜スラブ登はん開始~15:30終了~16:20水場~22:00宇部
三浦氏の記録から
午後は比叡の新ルート白亜スラブ。グレードは相当高く難しそう。実際の登攀も相当困難なものだった。水流渓人氏と小松の親分さんにも出会った。
前日の敗退から一気に復活。ロープワークに課題はあったが岩登りの楽しさを実感できた。
また宮崎に行きたい。
むすび投稿リポート

ロープ、梯子は随所にある。また岩峰もみんな登れ面白い。
上わく塚から大崩の笹ヤブ漕ぎには参った。
紅葉はあと2週間か。
下山道で見た小積ダキにはクライミングパーティーが2組。
次はクライミングだ。
前夜の夜空は周囲に明かりがないからかすばらしい星空が広がっていた。
午後はジョギングに。1時間とちょうどよいルートだ。
それにしてもクライミングやりたい!

比叡3h30m
1ピッチ目は小さな葉っぱで少し滑るのとロープの重さにまごつく。その後慣れ6ピッチまで気持ちよくリードした。クライムダウンし大滝で喉を潤しそれ以後は三浦氏がリードする。
がんばれば自分もなんとかリードできそうに思った。
午後は比叡の三峰左方カンテバリエーション。
ところどころ濡れている。
1Pクラックを登りハンドトラバース。ロープの流れが不自然でかわすのに時間を食う。
3ピッチで濡れたクラックを無理してレイバック気味に登りはがされぶら下がる。
足元には何もなく9mmロープ1本で恐怖を味わう。
最終ピッチは濡れてしかもコケでぬるぬるし相当怖い。
三浦氏もフレンズを持ってこなかったので20m近くランアウトし怖かったとか。
それにしても綱の目川までの高度感はものすごい。
50m懸垂を3ピッチで下山した。
これくらいのピッチがリードできるといいのだが、はたしてそんな日が来るのだろうか。
リードをやってやっと入り口に立てた気がする。
アルパインは楽しい。これからもがんばろう。

一般41名
会員13名
始ー9:55/10:07夏焼峠ー10:45/55休憩ー11:07立山尾根分岐ー11:12恐羅漢山、登山者多数、昼食ー12:10発ー雀蜂が一
匹、ー13:10/20台所原ー14:10/20管理林道終点ー14:36縦走路ー14:52夏焼峠ー15:20牛小屋高原Pー15:45帰路、16:
30/40来夢戸河内ー17:00/15吉和SAー18:45小郡ICー
松尾清氏の記録より
先頭を中原氏手作りの旗を持って進む。後ろの様子を図りながらペースを作る。
山頂では恒例の鍋のサービス。
台所原に降りるあたりから列がバラけだしたらしい。台所原では最後尾と15分くらい差がついてしまった。
その後も遅れるものがいるらしく相当遅く歩いてもコントロール出来ない。
一般登山者がたくさんいると実力に相当なバラつきがありその難しさを痛感した。
ともあれ総括を待たなければならないがまずは大成功と思った。
さて来年はどうする?

管理棟側でテントを張る。
ビールの後20度の焼酎を3人で1升空ける。
翌日酔いが残りリードをあきらめる。
今回雌鉾初めての3名もがんばって登り感動の山頂となった。
酒の飲みすぎは気をつけよう。
山頂には誰もいなかった。

CL松尾和代、SL田端、原田、門田、松尾清巧、森、佐藤、歳谷、福永、
藤中、吉野、岡野、永尾、横山、(以上会員14名)、川口(キノコ先生)、金子、
岡本、内田、中村、松本、横山ファミリー4名(以上非会員10名)合計24名、
車4台(松尾清、原田、福永、横山F)
合原でR191へ,9:50東八幡高原の千町原登山口着、往路121km、10:
08雨具着て川口さんを先頭に長蛇の列で登山開始、10:25馬返し(沢の二股分
岐)、岡野さんがキノコ発見歓喜の声が静かな森にこだまする、クリタケの群生だっ
た、しめしめ早速採取、11:40菅原林道終点の雪霊水、水汲みに車が次々にあがっ
てくる、雨が降り出し山頂でなくそこで昼食準備、ブルーシートを張る、食事係以外
は臥龍山の山頂に空身で登るが雨と霰(あられ)が降り出す、寒くて着込む、下ごし
らえしてあった具にクリタケなどを追加したキノコ汁であったまる、二鍋が空になる
のにそう時間はかからなかった、天候悪いので掛頭山は省略、林道をあがってきた横
山車で運転手が車をとりに行って全員林道から帰路、14時~15時匹見やすらぎの
湯、17時すぎ山口着、往復253km、解散、
松尾清巧氏の記録より
クリタケ、チャナメ○○タケなど、他にもあったが忘れた。
山頂直下の名水の駐車場できのこ汁。
途中からアラレが降る。寒い。掛津山は中止し早々に下山。匹見温泉経由で帰る。
途中道を間違え奥谷経由となる。
イノシシを追いかけるなど面白かった。
一応六畳岩のある山頂も踏んだ。
松尾 清氏の感想
山にいる時が一番天気が悪かった、キノコは少し時期が遅かったが同定できたキノコ
は:クリタケ、ブナハリ(白、香りが良い)、ヌメリツバタケモドキ(白くぬめりが
ある、ヒダに波があるのがモドキ)、ウスキモミウラモドキ(山に入ってすぐにあっ
た)、ドクツルタケ(白い、一本食べても死ぬ毒キノコ、ンだれか持って帰った?)
途中夫婦?ずれに出会う。
彼らは空荷だが追い抜いていった。

ベテランリーダーなしの登山禁止の看板からハーネスを着け気合をいれ出発。
程なく懸垂。細い木2本を束ね支点とする。門田トップで降りる。
ルンゼ状の泥壁の危ういトラバースをリードする。
トラロープと木で支点を取り確保する。
稜線へ登り進む。滑る岩を越えると...行き詰まった。
引き返し懸垂。ん?、見たことある風景?。トラバースしたルンゼに出た。
もう一度稜線に出ると反対側に進めば正解だった。
危うい3m程度のグズ岩をトラバースする。
さらに進むと6mの岩が立ちはだかる。横川がリードする。登山靴はすべり怖い。フリクションがない怖さを思い切り味わう。
ローソク岩横を懸垂し細い稜線へ降りる。ぬれる岩と強風、細い稜線とかなり難易度の高い懸垂である。気を抜くとどこも命の保障はない。
いよいよ核心の25mの岩壁だ。クライミングシューズに履き替えリードを決心する。
濡れた岩と人生2回目のリードで結構緊張したがなんとか支点に到着。
門田がロープを積み忘れ9mm50m一本の為門田はタイブロック登攀となり途中リッジに行けばやさしいのだが行けずに少々難儀する。横川が最後の登ってくる。
頂上からの懸垂は2回(最初の1回はクライムダウンも可能)。最後の懸垂は片方が垂壁となっておりそちらに振られると振り子トラバースとなりかなりやばい。
懸垂の最初で岩が落ちそうになり、ロープに当たらないようにかわして落とした。
コルからヤカタガウド谷へ。途中のメガネ岩、紅葉がなかなかよい。ゴルジュの紅葉も。
岩のマルチピッチも楽しいが、これは総合力が要求されより登山に近い感じ。
気に入った。今度は天気のよい日に再訪してみたい。
アルパイン初級~中級にも手ごたえがあり好ルートだと思う。

16:00終了
しかし実際のところハイキングでの捻挫、転倒骨折、疲労などにより動けなくなることが圧倒的に多い。
今回は8月に台風中止となった訓練の再挑戦である。
いつものことではあるが、ハイキング層の理解のなさが問題だ。
集まったのはほとんど中核の会員。みんな岩をやるひとばかり。
まずは、模擬事故での緊急手当て。
自分が足、ひじを痛めたと主張しそれに対応する。三角巾の使い方、添え木、止血、テーピング。
負傷者心理として「大丈夫」と無理をしがちと言うこと。納得できる。
さらにザックを使っての搬送法を3種類。
陶山頂から広場までの搬出。門田氏が背負い自分が負傷者。
ロープで確保しながらだが、あの急斜面をよく搬出したものだ。門田氏のパワーに脱帽。
食事の後は意識のない負傷者を背負う方法。
非常に力が要りとても一人では無理。2人いてやっとだろう。ザックでの背負いをセットしてやるのがよいとの結論になった。
次は担架搬出。ストックと雨具3枚、ビナ、シュルンゲでセットする。福江氏が負傷者となる。
狭い登山道での搬出は幅を取るし、カーブが難しかったりとにかく搬出は大事だといまさらながら実感した。
最後は連絡法の確認。また、いざと言うときの体制も考えておく必要も議論された。
有意義な1日で、年に1度くらいはやはりやるべきだろう。
帰り際に忘年会予定の千坊川河川公園を見て帰途についた。

下降12:30
それでもリベンジできる確信は持てなかった。
前回の挫折感と困難さが強い印象で残っていた。
1~2ピッチは前回より難しい感じですでにかなり腕を使ってしまった。
3ピッチ目が天井ハングのリベンジ箇所だがこんなので登れるだろうか。
結局40分を要してやっとの思いでクリアーすることが出来た。
あとは楽?と思いたかったが最終もA2でかなり厳しかった。
終了点からは空中懸垂で気持ちよく?降りてきた。
それにしてもこれをリードできる人は多くはいないだろう。三浦氏の記録でも手ごたえのあるルートとの記述があった。
自分の体感で Ⅶ、Ⅵ-、A2、A2というところか。
なんといっても冬山は体力。そのためのトレーニングだ。
全てアスファルトの車道というのがイマイチだが、長距離を歩くにはよいコースだろう。

24 登攀開始10:00=14:30 4Pで登攀撤退
翌朝気がつくと8:15。
登攀開始は10:00となった。取り付きは草つきから右へ1mトラバースだが苔むした岩で最初のクリップがいやらしい。
門田リード。1Pをフォローで登り人工初リードの確信を得たのでツルベを宣言する。
2Pは最初の最上段が微妙なバランスで肝と冷やす。あとは順調に行く。
3Pは上部が少しかぶっている。ルート図では2、3ピッチをつなげ2Pとしてある。
4Pは力があればフリーで行く。ピンは最初少しフリーで途中からA1設定、最後がフリーである。
確保地点に着いて少々休憩し時間を見ると14:30。これでは到底完登は不可能。
ここで撤退となる。
50m懸垂3回で下山。途中では補強に6mmシュリンゲを補強する。支点はいずれも垂壁途中にあり確実な停止技術、自己ビレイが必要になる。
門田氏はシャントをバックアップとしていた。参考となるシステムである。
今回は撤退となったが、アルパインは撤退を考えながら登る必要を痛感した。
また初ツルベの記念の登攀でもあった。
帰りは順調に4時間とちょっとで帰り着いた。

全員で24人
雪崩は自然現象だが、科学的に発生のリスクを判断、回避することも可能。
また、雪崩ビーコンの体験もあった。
有意義に1日だった。
後藤氏の頑固なまでの安全に対する責任感に強く打たれた。
片道3時間
途中から2時間ほど林さんと歩いた。空荷の林さんと同テンポ。
運動靴は最後の1時間は相当足の裏が痛く難儀した。
登山靴がいいのかもしれない。
距離 往復26km
累積標高 1200m
万華鏡 10b
南峰デピタン 5.8
とおりゃんせ 10a
ダイアモンドクラック 5.8
まず、陶でアイゼン登攀訓練。広場横の岩で登攀。やはり登りにくい。2回やると少し慣れてきた。ズックに変えると簡単に登れる。アイゼンでの困難さを体感した。
ルベルソでの懸垂体験。10.2のダブルだが良く滑る。9mmだと怖いかもしれない。
午後は亀に移動。
1、万華鏡 10b 横川RP。自分はTPで最初は左手で支え、左足に乗り込みながら伸び上がり右手で上部をつかむ。難しい。体を岩に張り付くようにするのがコツ。
次は隙間に入りたくなるがグッと我慢しちょっとハングした上部に手がある。右足が不安だが立ちこみ手で強引に体を引き上げる。
次は手はあるが足がない。右足を置くのに左足を置いたらぶら下がるようになり出来なかった。三浦さんのムーブを見たら、左足をテラス部においたままに右足をグッと上げて(上がらない)右足を利かせ登るようだ。結局出来なくてギブアップ。
2、南峰デピュタン5.8 スラブでこれはリードでクリアー。ただし最後の終了点にかけるのが少し難しい。
3、とおりゃんせ 10a 同じスラブの隣のルート。TPでやったがリードでもいけるような気がした。終了点が微妙なバランスと微妙な距離で難しい。
4、ダイアモンドクラック 5.8 これが5.8!!。最初のムーブが出来ない。残念ながらギブアップ。
なんといっても柔軟性とパワーが足りない。分かっているがなかなか改善しない。
ぼちぼちやるしかない。

P=45=稜線=35=山頂
下りは水は捨て、観音寺ルートへ
1h20m
山頂は前回(昨年 9月)より整備され、テーブルもあった。誰もいないので早々に引き返す。途中空荷の高年女性と出会う。背中のタンクを見て不審そうな顔。
観音寺登山口へは山頂から35分程。車道に出たの右に曲がったがあとで見ると大遠回りだった。
結局帰りもほぼのぼりと同じ時間を使ってしまった。
02年2月24日 晴れ
周防の森ロッジ登山口=45分=稜線=35分=虎岳
03年2月15日 晴れのち曇り
周防の森ロッジ登山口=29分=稜線=27分=虎ヶ岳
03年9月28日
周防の森ロッジ登山口=28分=稜線=30分=虎ヶ岳
今回
周防の森ロッジ登山口=45分=稜線=35分=虎ヶ岳。
くしくも2年半前、まだ山岳会に入っていない時のタイムと同じ。だが、今回は21kgのタンクを背負ってだ。これでも普通の人よりは少し速いコースタイムなのである。まずまずと言うところか。
観音ルート登山口に車を置き出発。25分で稜線と周防の森ルートよりずいぶん楽。
途中空荷のダブルストックの人に出会う。山頂には夫婦らしき2人。茶臼山から来たとか。
福江氏から電話が入る。冬合宿の打ち合わせでしばらく話す。
観音ルートだと茶臼山とほぼ同じ時間で、傾斜があるのでこちらのほうが良いトレーニングになるかもしれない。
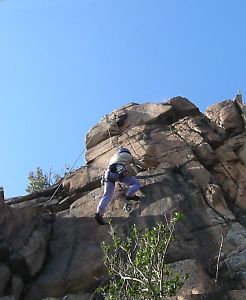
犬も歩けば 10b
陶 国体1ピッチ アイゼン登攀
9時すぎから南峰へ上り、9時半ころから登攀を始める。
永尾、北村、三浦は南峰デュピタンやっていた。
ビスケット&クラッカーにTRを三浦リードで張る。
右、左、中のルートの取り方で5.7~5.9となる。中が一番難しい。
次は犬も歩けばをTRで。
下部はたいしたことはない、が思ったよりテラスに登るところがいやな感じだった。
上部は垂直でホールド、スタンス少ない。ホールドはカチ。足はスメア。
結局A0とTRのロープのテンションでなんとか上まで。
亀山頂で林さんの調理で雑煮を食う。
そこから20kgを背負って陶ヶ岳までボッカ。
陶ではアイゼン登攀を行う。
林も挑戦するが相当苦労する。
Ⅲ級だがアイゼンと手袋をつけて登るとⅥくらいに感じる。
岩、ボッカ、アイゼン登攀と盛りだくさんだった。
さて、明日のボッカはどこにしようか。
平日でこれだけ人がいる山は山口では多くはない。
夏にやったときは1時間近かったから、大分ペースも速くなってきた。
これで冬合宿前の最後のボッカ。あとは雪を待つのみ。

ニードル左岩稜ノーマル
ウォーターカップ
TAカンテ
29 曇り
30晴れ
28日 7:40 船山十字路発~8:20旭小屋8:30~10:45立場山~10:50青ナギ11:30~12:25無名峰~12:45P1P2のコル。
29日 テン場発?~8:40P3コルに取り付く~11:30阿弥陀岳山頂11:40~12:30中岳~?文三郎分岐~14:30行者小屋
30日 7:20発~9:50赤岳山荘~10:30?八ヶ岳山荘(登山口)